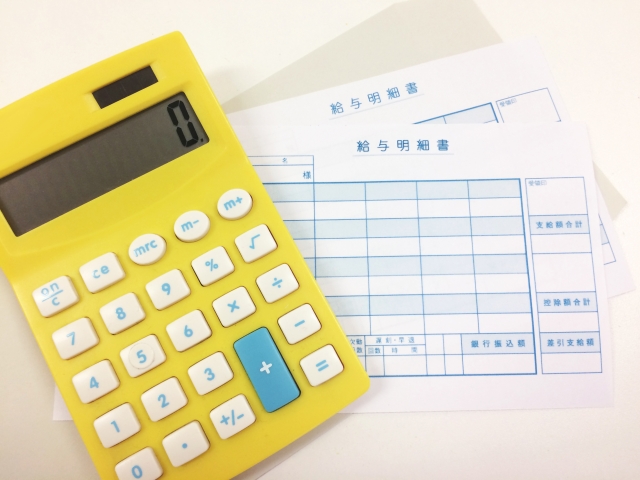
国会では裁量労働制の拡大について働き方改革方法から除外されましたが、「裁量労働制」であるかどうかは別として、「時間給」から「成果給」への移行は避けて通れない時代の流れであると思います。
目次
創造的な仕事と決断する仕事以外は「AI」や「RPA」に取って変わられる
先日に「AIに仕事が奪われるというが、仕事のニーズは変化していくもの」という記事を投稿しました。その中で、「AIに仕事が奪われるというけど、要は単純作業、繰り返し学習できる仕事が奪われるということ。そういう意味ではすでに仕事は奪われている」と私は書きました。
その記事を書いた直後の3月11日の日経新聞にて「事務用ロボ 日本でも普及」という見出しの記事がでました。
私は勉強不足で知らなかったのですが、パソコンを使う作業を自動化するソフトウェアを「RPA(ロボてぃっく・プロセス・オートメーション)」というそうです。工場で起きたような自動化の動きがホワイトカラーに及ぶとの記事です。
単純事務作業は人の手を離れつつある。例えばテープ起こしなどGoogleドキュメントでできてしまう
少し前に、取材などをする人の間では、Googleドキュメントによるテープ起こしが便利ということが話題になりました。取材で録音した内容などをテープ起こしするという仕事は昔からある仕事です。
それが、Googleドキュメントを活用すれば、無料で正確に早くできるという話です。詳細については下記の記事を読んでいただければと思いますが、
よく「AI」に仕事が奪われるというのは、「RPA」のことをイメージしているケースが多そうです。
日本の労働制が低いのは、「RPA」の導入が遅れているから?
このように、パソコンが自動でできる領域というのが広がっています。このような仕組みの導入は日本は欧米に比べると10年遅れているそうです。
この記事によると日本企業のホワイトカラーの業務の6割は定型化でき、8割は「RPA」で代替できるそうです。つまり、ホワイトカラーの約5割の仕事がなくなるということです。
日本の労働生産が低いのは日本の企業文化などが要因としてあげられるケースが多いですが、欧米でホワイトカラーの定型化された無いとしたら、日本の労働生産性が低いのはもしかしたら、これが要因かもしれませんね。
「RPA」の導入が欧米に比べて遅れている要因については記事内に書かれていませんでしたが、想像では、企業内における仕事を奪われる人の抵抗であったり、導入することによって余剰人員を抱えてしまうという問題とともに、日本語という問題が大きいと感じます。
例えば、文字の処理において、英語圏の方が広くGoogle等の企業も英語から対応するということともに、アルファベット26文字を処理できれば良いのに比較して、日本では、ひらがな、カタカナで100文字、さらに漢字があるので、その点が障壁になっていそうです。
創造的な仕事と決断するスキルを高めないといけない
さらに「事務用ロボ 日本でも普及」という記事の下には、「仕事の7%消える」という記事もありました。
この記事によると2020年までに日本の労働力人口の7%の仕事が自動化され、22%の仕事の内容が大幅に変わるそうです。
決められた時間で給料をもらえる時間給は単純作業の考え方
時間給というのは、働いた時間分だけ給料をもらえるという考え方ですが、これは、時間と成果が一致している場合に適応することが正しいです。また、時間で縛れる仕事の場合にも時間給が適応されるのが正しいです。
例えば、ショップ店員の場合には、「お店にいて受付をする受付対応」の仕事と「接客、販売」の仕事があります。いくら接客能力や販売能力が高くても、必要な売上をあげても仕事を切り上げてお店を閉めるわけにはいきませんから、「受付対応」部分の仕事は時間給である必要があります。一方で「接客、販売」の仕事は成果に応じて、給料を変える成果給にすることで従業員のモチベーションの維持とともにある意味の公平さが保てるのだと思います。
マクロなどで自動化する社員を評価する社風にしないといけない(少々、グチ)
「RPA」の導入というと、大企業だけができるのではないかと聞こえますが、中小企業では、エクセルのマクロや、先にあげたGoogleドキュメント、イメージスキャナやデジタルカメラで文字を読み取るOCRなどを活用することで自動化を実現できます。
20年ほど前に働いていた会社で、エクセルのマクロを使って、これまで数日かかっていた仕事を数分で終わるようにしたことがあります。
その結果は、評価されるのではなく、仕事が増え、これまでその仕事をしていた人にはやっかまれるという経験があります。
特にパソコンに弱い人が多い会社では権力を持つ中高年にこの傾向があります。そして能力のある若者が退職していくということがあります。
どんどん自動化を推奨する社風にしていく必要があると思います。
では、どんな仕事が残るかと言えば、創造する仕事と決断する仕事【ソリューションとジャッジメント】
前職では、ソリューションとジャッジメントの無い仕事は価値が無いと言われていました。まさにこれから残る仕事は、そうなのだと思います。ちなみにソリューションとは平たくいえば「問題解決」です。
つまり、問題を解決するような創造的な仕事かコンピューターでは判断できない決断をする仕事だけが残っていくということです。
「裁量労働制」は労働者の敵だといわんばかりの人がいますが、時間給で評価できる仕事が減りつつあります。どれだけ抵抗をしても、その事実だけは変えることができません。
「成果給」を受け入れたうえで、その制度を悪用する企業などが無くなり、多くの人が平等に評価される(平等な結果ではない)社会にコミットしかないといけないのではないかと思います。


